介護の世界は何かと言葉や制度・説明が難しいものが多すぎると思いませんか?
介護には必須の【介護保険制度】について、17年の在宅介護の経験から少しでも分かるように説明したいと思います。
今までの介護経験の話も挟みながら、少しでも理解できるような記事になれれば幸いです。
介護とは

まずは基本中の基本『介護』とは。
何を基準に、どこを境に介護というのでしょうか。
老齢または心身の障害により日常生活が困難な人に対して生活の自立を図ることを目的として『日常生活動作』、『家事』、『健康管理』、『社会活動の援助』を行うこと。障害者の生活支援をすること。または高齢者・病人などを介抱し世話をすること。
と、一般的に記されています。
分かりやすく説明すると、ご家族や身内の方が高齢や病気・事故などで
・身の回りのことが自らできなくなった
・普段の生活が1人でできなくなった
という状態になってしまったら、できない部分を補う、手助けすることが「介護」ということになります。
など、普段の生活で今まで1人でやれていたことができない状態になってしまった人に対して、それらを手伝う、できるようにサポートすることです。
わが家の場合
義母は脳出血で倒れ左半身麻痺状態になり、それ以来寝たきりの生活になりました。
義母が生活していく上で全ての事に介護が必要な状態になり、完全に1人では生きていけない状態です。
・食事
・歯磨き
・入浴
・排泄
・着替え
・寝返り
・移動
等々、普段の何気ない生活のほとんどが、病気によって全くできない状態になってしまったのです。
ちょっと極端な例になってしまいましたが、僕の義母の場合は全介護・全介助が必須の状態です。
介護保険制度とは
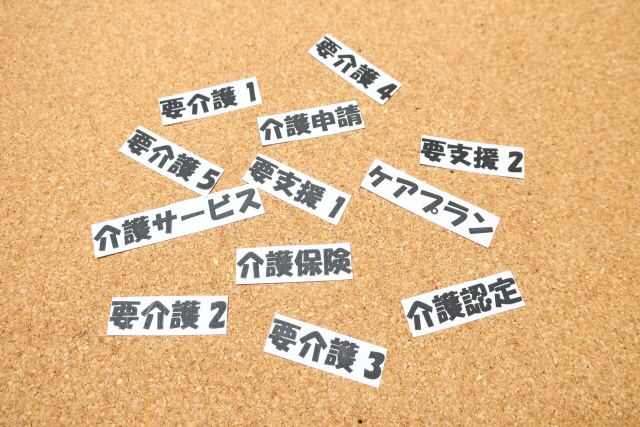
介護が必要となると、1人で要介護者を看るには限界があります。
そこをサポートしてくれる介護保険制度というものがあります。
では実際にどんなものなのかみていきましょう。
介護保険制度の概要
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。少子高齢化や核家族化に伴い、被介護者を家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、被介護者の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・被介護者の双方が安心して生活できる社会を目指し、平成9年12月に「介護保険法」が制定され、平成12年4月から施行されています。
介護をする側にとって介護保険制度がないと共倒れになってしまいます。
もし介護保険制度がなかった場合を想像してみて下さい。
もし保険制度がなければ
もし夫婦2人暮らしで、夫が倒れ介護が必要な状態になったら、一般的には妻が夫の介護をすることになります。
そうなると夫の介護度合いにもよりますが、
・妻1人だけで看れるのか?
・生活費などの収入はどうするのか?
体力的・金銭的・精神的な問題が出てきます。
そういう問題を減らそうということからつくられた制度です。
ありがたいですよね。
なぜ「介護保険制度」がつくられたのか?
今から40年以上も前は親戚や近所には、おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に住んでいる3世代家族が今よりも多くいました。
実際に僕の親戚にも、自宅に介護ベッドをおいておばあちゃんを介護している家族がいた記憶があります。
その頃は、介護保険制度がなくても誰か看れる家族が多かった時代。
しかし時が経つにつれ、少子化や核家族が増え、働き方などもかなり変わってきました。
共働きも当たり前になり、介護が必要となった家族は経済的負担や精神的負担が増え、介護離職者も増えてくるなどの社会現象にもなったわけです。
そんな問題に対応するために、この「介護保険制度」ができました。
介護に理解が増えてきたり話題が上がるようになってきたのは、本当にここ最近ですよね。
わが家の場合
ちなみに僕の義母の場合は何かしらの関係があったのか、皮肉にも義母が脳出血で倒れ介護が必要になったのは介護保険制度が始まった2000年です。
不思議なタイミングです。
その制度ができたおかげで、僕ら夫婦も上手に介護サービスを利用して義母を最期まで看れたということになります。
義母が倒れた時は、まだ僕と妻は知り合ってなかったので仕事をしながらの介護。
もちろん介護施設で看てもらっていましたが、介護保険制度がなければ当時の妻の生活もかなり酷いものになっていたと思います。
介護が必要になった時にみんなで助け合えるようにつくられた「介護保険制度」。
今の高齢化社会には、なくてはならないものです。
上手に利用していきたいですよね。
介護保険とは
介護保険制度を利用するには介護保険が必要で、以下の3つの柱を基本に成り立ちます。
- 自立支援身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポート
- 利用者本位被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる
- 社会保険方式に納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける
介護保険の対象者は
介護保険の対象者は年齢で以下のように区分けされます。
- 第1号被保険者
65歳以上で介護が必要であると認定を受けるとその程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。 - 第2号被保険者
40歳~64歳まで ※39歳以下の人は介護保険を利用できません※
末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ介護給付を受けることができます。
介護保険は40歳になった月から、全ての人が加入することになり支払い義務が生じます。
会社員の人であれば、40歳になる月から毎月給料から天引きされます。
最後に
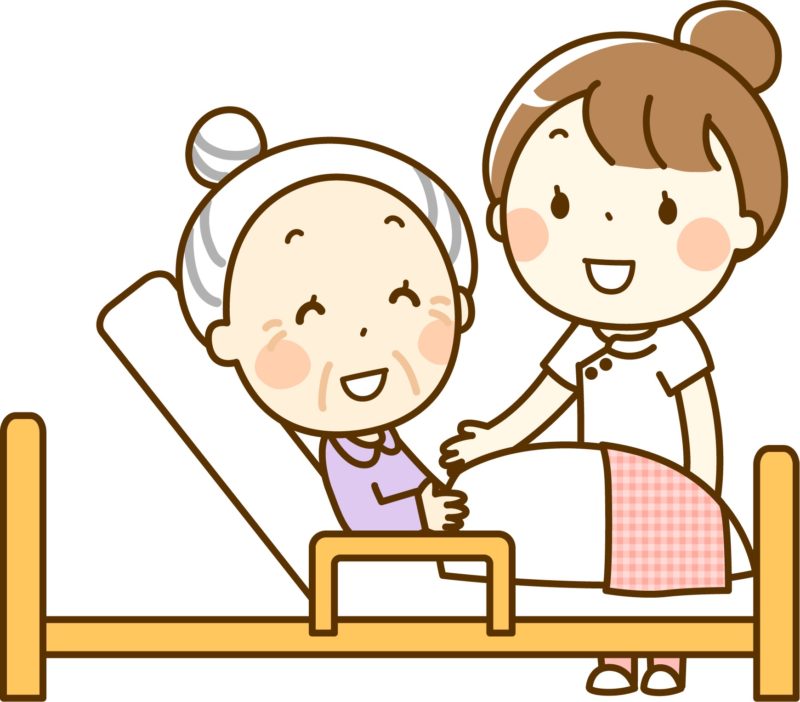
介護と聞くと高齢の方が対象というイメージが強いですが、40歳から介護保険制度の対象者になり少しは身近に感じるのではないでしょうか。
40代でも何が起きるか分かりません。
個人的に入る保険ももちろん大事ですが、国で守られている介護保険制度。
ただ40歳から64歳までの第2号被保険者が注意したいのが、介護保険を使えるのは【16種類の特定疾病】のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみという条件。
生活に支障がでるからと、第1号被保険者と同じように介護サービスを使えるわけではありません。
この辺も目を通しておいた方がいいですよね。
わが家の要介護5の義母は、寝たきりで完全に介護が必要な状態なので、介護保険制度があってかなり助かりました。
この記事が、初めて介護に携わる方の少しでも一助になれば幸いです。
- 介護をするには介護保険制度は必須
- 介護保険制度を利用するにあたりしっかり理解しよう
- 第2号被保険者(40歳~64歳)は介護保険制度を利用するには注意したいポイントがある




コメント